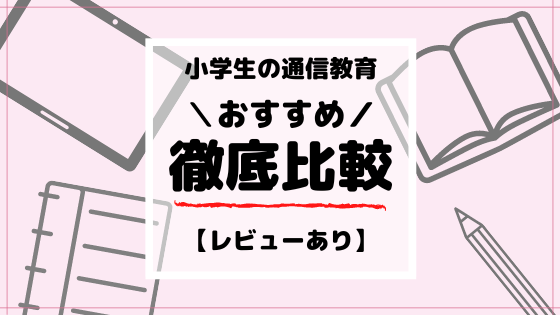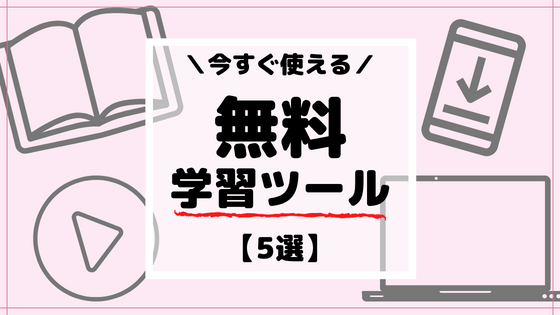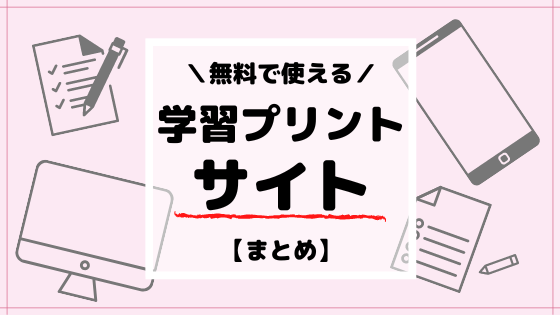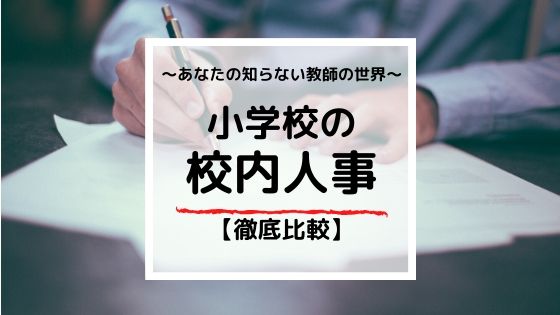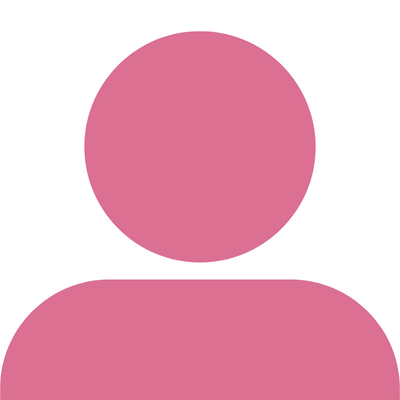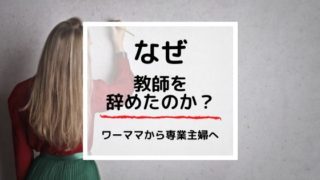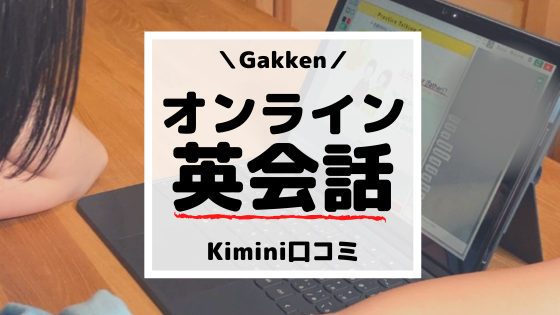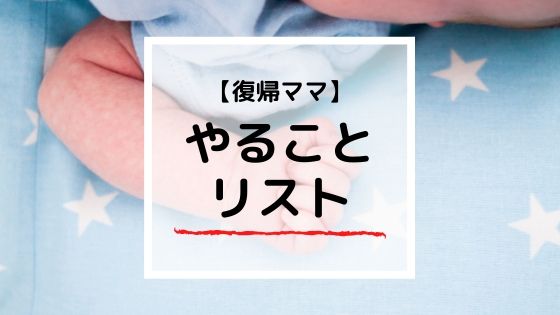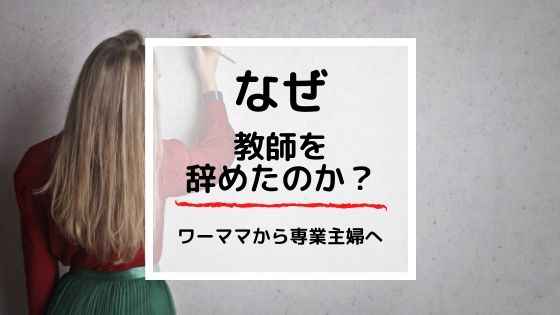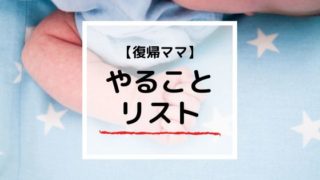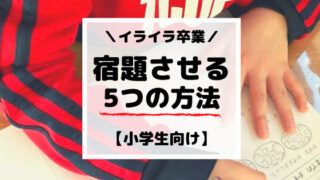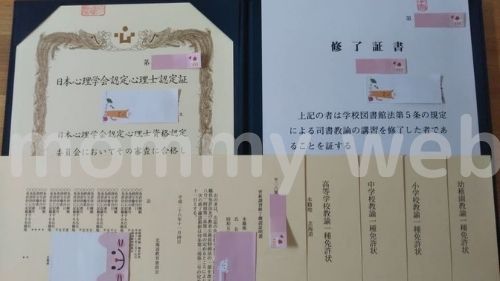校内人事を決める時期が憂鬱…
どのポジションが自分にあってるんだろう?
小学校の校内人事を決める時期になると
職員室内がざわつきませんか?
- どのポジションが楽なのかな?
- あの先生と組むのだけは勘弁…
- 特別支援ってどうなんだろ?
結論を先にお伝えすると
小学校教師に、楽なポジションはありません!!
また、校内人事のポジションで
仕事できる・できないは、判断できません!!
- 小学校教諭の校内人事ポジション
- 校内人事ポジション別の仕事内容
- 校内人事ポジション別のメリット・デメリット
- すべての校内人事ポジションについた元教師の体験談
教員歴10年!
すべてのポジションについたことのある私が、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較します!
この記事を読めば、学校の先生のボジションについて丸わかりできますよ♪
小学校の校内人事の誤解あるある!

- 担任の先生になる人が、仕事ができる人。
- フリーの先生は、仕事ができない人。
- 特別支援の先生は、大人数の子供たちを、まとめられない人。
そんな固定観念おもちの方
いらっしゃいませんか?
自分が小学生の子どもがいるママの立場になり
周りの保護者に誤解されてることに驚きました…
でも、現場で働く先生も同じように感じている部分があるのでは…
正直、校内人事の決め方は
- 校務分掌との兼ね合い
- 先生の経験や年数
- 複数学級なら、組む先生とのバランス
- 先生自身の家庭環境
などなど、たくさんの要因から、校長先生の判断で決められます。
簡単に、仕事ができる・できないだけでは、決められません。
※ 何をもって、仕事ができる・できないを決めるかも微妙ですが…
だから、声を大にして言いたい!
ポジションだけで先生の良し悪しを決めるな〜!!!
小学校教師のポジション!どんな種類があるの?

では、小学校教師のポジションってどんなものがあるのでしょう?
具体的に仕事内容とメリット・デメリットを私の体験談を元に紹介していきます。
ちなみに、私は高学年の担任以外、ぜんぶ経験しました!
学級担任~低学年~

2年生の担任は、個人的に好きです!
子どもも保護者も学校生活に慣れてきた、発達段階的に素直に先生の話を聞く子が多いという点から考えると、持ちやすい学年だと思います。
学校ルールや学習規律が整っている持ち上がり学級だと天国ですね。
でも、同じ低学年でも1年生は大変です。
子どもは幼稚園や保育所など、いろいろな環境から集まってきます。
それぞれのルールを、学校ルールに統一し、定着させるために力を注ぐ必要があります。
小学校生活の基盤を、この1年間で身につけさせなくてはならならないので、きめ細やかな対応が必要です。
特に学習規律を徹底できると学年が上がっても安心ですが、学習規律が不徹底な場合は、後々受け持つ担任が大変な思いをします。
もちろん、子どもだけでなく、保護者も初めての学校生活です。
今まで、見えていた子どもの生活環境が急に見えなくなり、心配になる保護者も多いです。
特に第一子の場合は、なおさらです。
毎日の授業内容や揃える道具など、細かいところまで見えないので、心配になります。
上の子どもが小学校入学した時に、ママ友に授業道具や登下校など、よく相談されました。
私自身、自分が保護者の立場になって、改めて気がついたことがたくさんあります。
当たり前に伝わる、分かるだろうと教師側が思っていても、以外に保護者には伝わっていないことが多いんだと分かりました。
そのくらい、1年生の担任は細かい指導や保護者への連絡を大切にする必要があります。
デメリットばかり書いてしまいましたが、1年生の最高のメリットは、何と言っても「かわいい!」これに尽きます。
学校での初めての勉強!新しいことを覚える喜び!勉強が分かる楽しさ!
毎日、目をキラキラさせて「せんせ~!」と話してくれる子どもたちは、とてつもなくかわいいです!
学級担任~中学年~

3年生になると、急に学習が難しくなるように感じます。
今まで当たり前に分かっていた授業も、よく考えなくては答えられなくなります。
特に算数では、積み重ねと応用力が試されるため、学力にばらつきのある学級を持つと個々の対応に追われ、担任は大変です。
また、中学年から理科・社会・外国語活動が始まります。
外国語活動は、全ての授業に外国語講師やALTが入ることは少ないです。
学級担任が英語を話して、授業することになります。
英語が堪能、クラスルームイングリッシュ程度は使えるのなら問題ありません。
私は英語が、いちばん苦手…
という小学校教師には、厄介な問題です。
細かいことですが、3年生の社会科は、私たちの地域を学習するので、新しい学校に赴任し、地域についてよく分からないという場合は、下調べに時間がかかります。
そういう小さな積み重ねが、大きな仕事量となります。
中学年のメリットは、先生と子どもの縦繋がりから、子どもと子どもの横繋がりが増えることで、学級活動などを活発に行うことができるようになることです。
行事に向けて子どもたちがアイディアを出し、目標に向けて頑張る姿は、担任として誇らしく感じられます。
学級担任~高学年~

高学年になると子ども対大人ではなく、大人対大人の会話になります。
子どもたちと信頼関係を上手に築けると、毎日のやりとりが楽しくなります。
6年生は、当たり前ですが卒業式があります。
「卒業式マジック」という言葉を、先輩先生がおっしゃっていました。
どんなに辛くても、卒業式を迎えられると美化され、達成感が半端ないと(笑)
子どもたちや保護者の方々に感謝され、涙している卒業担任を見ていると、素敵!私もいつか卒業生を出したい!と思ったものです。
高学年のデメリットとしては、家庭科、外国語科などさらに教科が増えることです。
家庭科も外国語も授業準備が掛かる学習内容が多いため、放課後の授業研究に時間を取られます。
また、児童会活動の中心としても子どもたちを指導しなくてはならないため、学校全体を把握し、進めていかなければなりません。
先生自身が学校行事や流れを知っていることが必要になります。
赴任したばかりに6年生を受け持つのは力のある先生でないと、難しいように思います。
特別支援学級担任

人数が普通学級より少ないので、指導が簡単に思われがちですが、そうでもありません。
一人ひとり個別の指導計画を作成し、細かな配慮が必要になります。
合理的配慮と言われるようになった今、特に障害のあるなしに関係なく、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害や困難さを取り除く教育がより求められます。
保護者と定期的に面談し、要望を聞き、連携をとっていく回数も多いため、授業の準備などの時間は少なくて済むかもしれませんが、その他の業務に時間が掛かる場合があります。
通常学級が全体あっての個の指導ですが、特別支援学級は個あっての全体指導の意味合いが大きいように感じます。
(通常学級でも個はもちろん大切だと思っています。)
また、特別支援教諭の免許がない先生が特別支援学級担任を持つ場合は、専門的な知識が少ないため、日々勉強する必要があります。
私がまさに、そうでした…
生活単元って?自立活動って?違いはなに?というように、はてなマークがいっぱいになりました。
最後に、残念なことに通常学級の担任を持たせられない先生が持つポジションという、古くからの体質が未だ残っているということです。
そのため、仕事ができない、何もしない先生と組むこともあるので、注意が必要です。
同僚との相性が合わないという場合も考えられるのです。
専科・TT・フリー

専科は理科専科や音楽専科など、私が赴任した学校にはありました。
そして私は、初任者時代、音楽専科とTTを兼務で持っていました。
専科は自分が得意分野であれば、その知識を思う存分発揮できるので、やりがいを感じられます。
逆に、全くの分野外の場合は、毎日の授業準備が苦痛になることでしょう。
TTは、色々な学級に入って指導の補助をするため、先生の指導を見られるという利点があります。
教師経験が少ない先生にオススメです。
また、フリーは教務主任など、校務分掌(学校を運営するための仕事)が大変なため、経験豊富の先生がなることが多いです。
次期、教頭になる先生が、多く付くポジションですね。
私が初任の頃は、早く学級担任を持ちたくてウズウズしていましたが、色々な先生方の指導を間近で見られた1年間は、後の自分の指導に大いに役立ちました!
学校の先生は、職人だと思います。
師匠の技を見て学べ!
みたいに、先輩先生の授業や学級経営を見て学ぶのです。
今の大学は違うのかもしれませんが、大学で教わった教育課程の授業は、教育現場ではほとんど生かされません。
細かな指導案を毎時間作成する先生は希です。
それよりも、1日6時間の授業をどのように準備し、子どもに効果的な話し方伝え方はどのような指導なのかを具体的に教えてもらいたいたかったなと思います。
そのため、初任の先生にはTTが本当にオススメです!
デメリットは、担任の先生によってTTの先生や特別支援の先生に対して、冷たい扱いをする場合があるということです。
先生によって対応の温度差があります。
担任以外は余計な口出ししないでと言われることも、担任以外でも、もっと入って指導してとも言われるので、その先生個々によって接し方が難しいのです。
これは学習支援員の先生もよくストレスに感じる部分だそうです。
担任の先生との相性、指導の方向性や介入の仕方など、考える必要が出てきます…。
校内人事【小学校教師のポジションを徹底比較】まとめ

結局、どのポジションがいいわけ?
となりますが、どのポジションも大変だということです。
何度も言いますが、楽なポジションはないのです!
2年生がオススメだと言っても、その年の子どもたちや保護者のカラーによって全然違います。
こんなことを言ったら語弊があるかもしれませんが、正直当たり外れの年や学級があり、乱暴な言い方ですが、くじびきだなと思うのです。
子どもたちや保護者がよい人たちが多くても、その時の同僚メンバーの連携が取れていなければ、学級経営もうまくいきません…
校内人事ですべてのポジションを経験した私が思うこと

私が約10年間小学校教諭として働いた経験から思うこと。
どのポジションでも、自分のできる部分は頑張り、できない部分は無理せず「出来ません」と言うことが、一番大切だということです。
自分の考えや指導方法を子どもや保護者、同僚、管理職に伝えることが大切だと感じました。
どうしても学校の先生は真面目な人が多く、できる!やらなければ!という人が多いように思います。
できる振りをすると自分はもちろん、結果的に周りも苦しくなることに…私がそうでした。
※ まだお読みでなければ、教師を辞めたい!後悔はしない?ワーママから専業主婦になった体験談 をご覧下さい。
校内人事でどのポジションについても、周りに合わせ過ぎす、自分の気持ちに正直に行動することが、先生という仕事をする鍵なのかもしれません。
ここまでお読み頂き、ありがとうございました。
2021/09/11
アキ